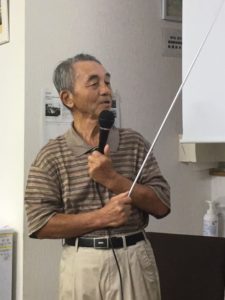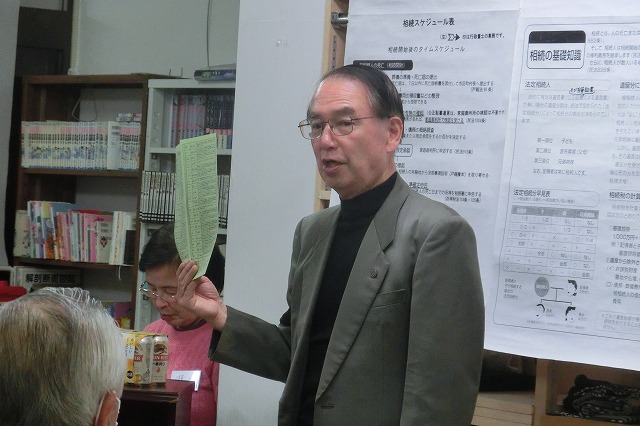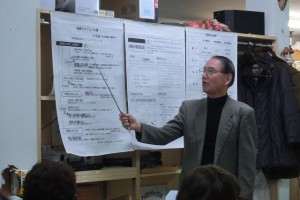演目は「代脈」、「甲府ぃ」でした
 9月の西柴夜話は落語でした。話し手は西柴夜話最多登場の春風亭三朝師匠です。
9月の西柴夜話は落語でした。話し手は西柴夜話最多登場の春風亭三朝師匠です。
いつものよく通る声で参加者を噺に引き込みます。演目は二題、ちょっと間抜けな医者の弟子に伊勢屋のお嬢さんのところに往診に行かせるという「代脈」、甲府生まれの若者が江戸にでて豆腐屋の婿養子となり里帰りするお話の「甲府ぃ」でした。本編に入る「まくら」の話では、天候の話やお年寄りの日常生活を笑いに代えたり、後半ではグアム旅行の際に経験したある航空会社の機内食をとりあげ会場を沸かせていました。
西柴夜話にはこれまで5回登壇いただいていますが、はじめて聞くという方も相当おりました。後半の交流会では「生の落語を聞けて良かった」「楽しかった」「先日テレビで師匠を拝見しましたよ」などの声が出されていました。質問もいくつか出され、屋号の解説もありました。落語界では屋号とは言わず亭号というようです。さらに同じ春風亭といっても(春風亭昇太と小朝の間には)一門の関係はないなどの解説がありました。
すっかりおなじみとなった三朝師匠、今後とも西柴夜話への登壇をお願いして「第七回さくら茶屋寄席」は終了いたしました。



富岡長昌寺に眠る郷土の宝を知ってほしい
6月の西柴夜話は直木賞に名を残す作家「直木三十五」に関する逸話やエピソードについて、西柴在住・鎌倉ペンクラブ会員の西内俊秀さんに語っていただきました。西内さんはもともと読書家、あるきっかけから直木と触れ合い「直木は金沢区にとっての大作家、郷土の宝を知ってほしい」と活動を始めたといいます。
 直木の本名は植村宗一、植の名を分解したペンネームが直木、三十五についても解説します。明治24年に生まれから昭和9年に亡くなるまでの43年間の波乱万丈の人生やエピソードをスライドで示しながら紹介していきます。
直木の本名は植村宗一、植の名を分解したペンネームが直木、三十五についても解説します。明治24年に生まれから昭和9年に亡くなるまでの43年間の波乱万丈の人生やエピソードをスライドで示しながら紹介していきます。
大阪生まれの青春時代、菊池寛との運命の出会い、年上の須磨子との同棲生活、複数の愛人と関係、派手な生活と借金でピーピー生活の様子、その借金が関東大震災でご破算になった逸話、映画にものめりこむが撤退などなど、波乱の人生が語られました。しかし時代小説家としては第一人者で多くの文壇人に影響を与えたといいます。それなのになぜ知名度が薄いのか、そこも西内さんなりに解説されます。亡くなった後に戦争が相次いだこと、注目される子供たちが若くして亡くなったなどなど・・・。更に、なぜ終の棲家を富岡に求めたのか。いろいろ憶測はあるようですが、時代小説家として数多くの逸話がある横浜の地を選んだのではというのが西内さんの説。
その後料理を囲んでの交流会では、直木賞の由来や仕組み、映画とのつながり、無口な直木がなぜ6人もの女性にもてたのかなどの質問があり、参加者の感想も含め交流しました。お墓のある富岡長昌寺、また行ってみようそんな感想が出されていました。



10名に加え、急遽飛び入りもありました
 6月の西柴夜話は、女性陣10名に「詩吟」を披露していただきました。山下まり子さん(不識庵機山を撃つの図に題す)、長谷川伸子さん(幾山河)、久保田千栄さん(富士山)、岡本溢子さん(寒梅)、福田有美さん(山中にて幽人と対酌す)、玉井洋子さん(子等を思ふ歌一首)、高野功子さん(同じこころ)、栗山紀世子さん(名鎗日本号)、菊池弘子さん(雨ニモマケズ)、嶋慶子さん(夢 & 閑かさや)、その他、3名による合吟、全員での合吟がおこなわれました。多少時間に余裕もあったことから、急遽参加者で詩吟を習っているという方3名からの歌いもありました。
6月の西柴夜話は、女性陣10名に「詩吟」を披露していただきました。山下まり子さん(不識庵機山を撃つの図に題す)、長谷川伸子さん(幾山河)、久保田千栄さん(富士山)、岡本溢子さん(寒梅)、福田有美さん(山中にて幽人と対酌す)、玉井洋子さん(子等を思ふ歌一首)、高野功子さん(同じこころ)、栗山紀世子さん(名鎗日本号)、菊池弘子さん(雨ニモマケズ)、嶋慶子さん(夢 & 閑かさや)、その他、3名による合吟、全員での合吟がおこなわれました。多少時間に余裕もあったことから、急遽参加者で詩吟を習っているという方3名からの歌いもありました。
出演者の詩吟の経験は、数か月の方もおれば、何十年と積み重ねている方もおられましたが、それぞれが個性を活かし演じられていました。どなたも背筋をピンと伸ばし、姿勢を正して堂々と歌われ、みなさんから大きな拍手が送られていました。
お料理やドリンクをいただきながらの交流会では、各々の経歴や詩吟を行うようになったきっかけなどが語られたり、詩吟の節回しを参加者全員で歌詞を見ながら歌ってみるなど、参加した方の中には詩吟に初めて触れる方もおられましたが、みんなで楽しんだ2時間でした。




瀬戸神社宮司の佐野和史さんのおはなし。
 大正・昭和初期の「金沢八景」の数々の風景写真を絵ハガキにしたものをスライドで紹介しながら、当時の様子や、現在との違いを解説していただきました。当時の写真は、すべて白黒ですが、絵はがきとして販売する際はそれに色を付けていたことから、紹介のスライドはカラー写真でした。埋め立て以前の風景や、野島に航空隊の格納庫があったことから野島運河がつくられたことなど、特に昭和一桁世代には懐かしい風景とお話しでした。
大正・昭和初期の「金沢八景」の数々の風景写真を絵ハガキにしたものをスライドで紹介しながら、当時の様子や、現在との違いを解説していただきました。当時の写真は、すべて白黒ですが、絵はがきとして販売する際はそれに色を付けていたことから、紹介のスライドはカラー写真でした。埋め立て以前の風景や、野島に航空隊の格納庫があったことから野島運河がつくられたことなど、特に昭和一桁世代には懐かしい風景とお話しでした。
後半は瀬戸神社にまつわるお話、源頼朝がこの地の伊豆三島明神を祀ったことが起源であること、鎌倉から江戸時代にかけてお寺が果たした役割、徳川家康が「関ケ原合戦」を前に会津討伐のため大阪から江戸へ向かう途中この地に寄り、その後東照宮が建てられたこと、江戸城本丸御殿の襖絵には立ち寄った際に家康が絶賛した金沢八景の風景が描かれていることなどがはなされました。
食事・ドリンクを囲んでの交流会では、「瀬」や「戸」の由来、瀬戸神社のこれまでの歴史、瀬戸神社お参りの際の作法などの質問が出され、一つひとつ丁寧に解説していただきました。時間が限られていたことから、現在の八景の再開発問題まで話は至りませんでしたが、新たにできる公園に「家康ゆかりの地」として像建築の運動などがあるようです。今度瀬戸神社に行った際は「改まった気持ち」でのお参りになる夜話でのおはなしでした。


植裁デザイナー、平工詠子さんのお話しです。
 4月の西柴夜話は植栽デザイナーでありプロのガーデナーである西柴在住、平工詠子さんの「球根ミックス花壇」のお話しでした。平工さんは大学卒業後、横浜で造園・園芸に従事していましたが、その後イギリスにわたり4年間、オランダでも半年間、球根による大規模な花壇づくりからメンテナンスなどを担当し実践してきました。現在は大学の講師として、あるいは横浜をはじめ各地で花壇づくりの指導から講演活動なども行う、今、注目のガーデナーの一人です。
4月の西柴夜話は植栽デザイナーでありプロのガーデナーである西柴在住、平工詠子さんの「球根ミックス花壇」のお話しでした。平工さんは大学卒業後、横浜で造園・園芸に従事していましたが、その後イギリスにわたり4年間、オランダでも半年間、球根による大規模な花壇づくりからメンテナンスなどを担当し実践してきました。現在は大学の講師として、あるいは横浜をはじめ各地で花壇づくりの指導から講演活動なども行う、今、注目のガーデナーの一人です。
当日は、「全国都市緑化よこはまフェア」などでの華やかな花壇の様子や、花の育て方など技術的な話もありましたが、わが街にある「西柴第一公園」の花壇づくりを地域の皆さんと協力して作り上げた様子をビデオで映写、その際の数々のエピソードを交えながら紹介してくれたことで、参加されたか方々はより身近に感じながらお話に聞き入っていました。チューリップといっても多様な種類があり、早咲きから遅咲きの球根を駆使し、色合いも考えながらいかに美しく、いかに長い期間人々を楽しませるかなどについて熱く語っていただきました。
飲食を挟んでの交流会では、参加者みなさんも「お花好き」の方々、お庭の園芸でいつも困っていることの対処法の質問や、近所づきあいで平工さんに花づくりをお手伝いいただいた方々の感謝の言葉などがだされ和やかな雰囲気で2時間を過ごしました。



知っておきたい!遺言と相続、
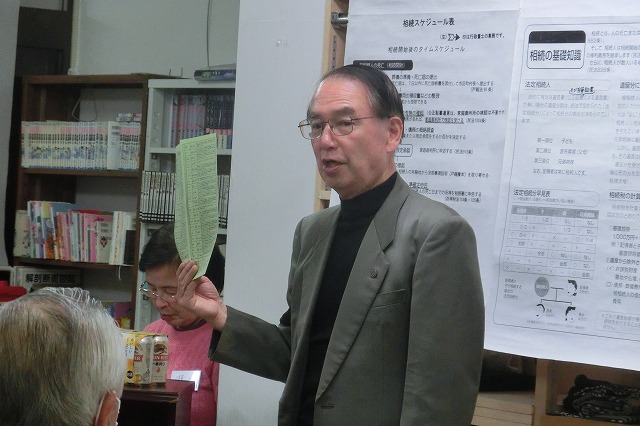 2月の西柴夜話は行政書士の新井克己さんをお招きしての「知っておきたい!遺言と相続」というテーマで語っていただきました。これまでの夜話とは違って「学習会」的な内容、そこでテーブル配置もいつもと変えて新井さんを囲むような形にしました。
2月の西柴夜話は行政書士の新井克己さんをお招きしての「知っておきたい!遺言と相続」というテーマで語っていただきました。これまでの夜話とは違って「学習会」的な内容、そこでテーブル配置もいつもと変えて新井さんを囲むような形にしました。
遺言書の種類、必要性や有効性、書くにあたっての内容の注意など。相続では遺言書がない場合の法定相続、平成27年に改悪された相続税の内容、相続開始から納付までのスケジュール等などです。今回の内容は、皆さんが身近になってきた問題だけに参加者も配られた資料に真剣にメモを取る姿が多くみられました。
食事をとりながらの交流の場では、時間が足りなくて一時間の中で聞けなかった後見人問題への質問などが出されました。ただこうした問題は、その人その人によってケースが違うこともあることから、みなさんのおしゃべりの間に、新井さんに個々に質問する姿がみられました。
夜話終了後の後片付けに多くの参加者がお手伝いいただくなど、アットホームな雰囲気でおえました。みなさんありがとうございました。
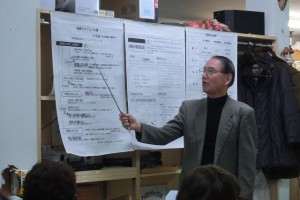


 12月の西柴夜話は一年半ぶりの登場、トニー山本さんと小柴ゆみえさんがコンビの「前途洋洋」さんでした。トニーさんがウクレレとパーカッションで軽快な演奏を、その横で小柴さんがノリノリの踊りとのびのある声で歌います。
12月の西柴夜話は一年半ぶりの登場、トニー山本さんと小柴ゆみえさんがコンビの「前途洋洋」さんでした。トニーさんがウクレレとパーカッションで軽快な演奏を、その横で小柴さんがノリノリの踊りとのびのある声で歌います。